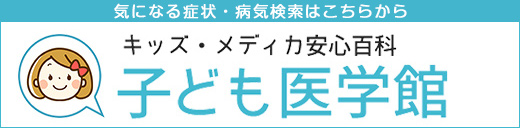「病気」は心が発するシグナル。心の声に耳をすませて
心の病気というと、「なんとなくこわいもの」といった偏見が、まだまだあるようです。しかし、心の病気は、特別な人がかかるものではありません。ストレスの多い現代人にふえている神経症や心身症などは、発症の条件がそろえば、だれでもかかる可能性があるものです。たとえ病気になったとしても、はじることなどありません。
病気は心が発するシグナルだという考え方があります。「いまのあなたは、自分らしい生き方をしていませんよ」と心が教えてくれているのです。
さらに、おもてに現れる症状は、心が運んでくるメッセージと考えられます。たとえば「気分が落ち込んでなにもやる気にならない」という症状は、「あなたは疲れすぎているから、少し休みなさい」というメッセージなのです。ときには、頭痛や肩こり、月経不順など、心のメッセージがからだの症状となって現れることもあります。
心の病気はだれでもかかるものという認識を持って、みんなで正しく理解し、対処していくことがたいせつです。心のメッセージが届いたら、あるいは心に不調を感じたら、かぜをひいたときに内科にかかるように、気軽に心の専門科を受診しましょう。
現代女性は、心の負担が大きくなっています
社会生活のなかでは、本来の自分を抑えなければならないことがあります。これは社会生活を送るうえでは、当然のことかもしれません。しかし、必要以上に自分を抑え込み、周囲のものさしに合わせていると、ストレスが高まって心身に影響がでてきます。
とくに女性の社会進出がさかんになった現代では、女性が男性と肩をならべて活躍する場が広がりました。しかし、その半面、「女性は、妻は、母は、かくあるべき」といった昔ながらの古い考え方を押しつけられることもあります。そのため、女性の心の負担は大きくなっているといえます。
さらに、女性には、結婚や出産、育児、夫の転勤、子どもの独立や親の介護など、世代ごとにさまざまストレスをかかえる場面もあります。心に負担を感じたら、ひとりでなにもかもかかえこまず、パートナーや身近な人と話し合って、負担を軽くしましょう。
また、ときには立ち止まって、自分は本来どんな人間なのか、ほんとうに望んでいるものはなにか、といったことを見つめることもたいせつです。
心の病気は、原因も症状も複雑にからみあっています
心の病気は複雑で、患者さんごとに異なる背景をかかえています。たとえば、同じような心理的なショックを受けても心に傷を受ける人と平気な人がいます。それぞれのパーソナリティー(性格、人格)のほかにも、その人をとりまく環境などが深くかかわっているものと考えられます。また、近年の研究では、脳の機能、とくに神経伝達物質が心の病気と関係していることもわかってきました。
このように、心の病気は、さまざまな要因が複雑にからみあって生じるものです。したがって、その症状も多様で、病気によっても人によっても異なります。まさに千差万別といえる心の病気ですが、一般的には、原因別に三つに分類されています。
脳梗塞(脳卒中のいろいろ)などの脳疾患や頭部の外傷で、脳が直接ダメージを受けて生じる「器質性精神障害」と膠原病(免疫の異常)や代謝異常(内分泌(ホルモン)・代謝の異常)などの身体疾患が原因で、二次的に脳がおかされて発症する「症状性精神障害」の2種類があります。
強い精神的ショック、人間関係など心理的な要因で起こります。神経症や心身症が代表的な病気です。
はっきりした原因がわからないため、「内因性」と呼ばれていましたが、現在では脳内の神経伝達物質の異常が原因の一つであることがわかってきました。統合失調症やうつ病、躁うつ病がこれにあたります。
心の診療科はいろいろ。扱う領域も少しずつちがいます
心の病気をみる専門科には、「精神科」「神経科」「精神神経科」「心療内科」「メンタル・クリニック」などがあります。
このうち、精神科、神経科、精神神経科は、ほぼ同じ診療内容で、心の病気全般を扱います。これらの診療科では、重い精神疾患にも対応できます。
心療内科は、精神的な問題が原因で生じるからだの不調を治療するとともに、簡単な精神療法も行います。
メンタル・クリニックは、開業医による診療所で、精神科の医師、心療内科の医師のどちらも開院しています。気軽に通える町の診療所といえます。
医療機関ではありませんが、臨床心理士などがカウンセリングを行う「心理相談室」も、心の問題を解決するために有効です。
なお、心の診療科とまちがいやすいものに、「神経内科」があります。こちらは、からだの「神経系」の病気をみる科で、心の病気は扱っていません。
心の診療科と扱う領域
・精神科(神経科・精神神経科)…心の病気全般
・メンタル・クリニック…軽い精神症状
・心療内科…精神的な原因で生じる身体的症状
・心理相談室…臨床心理士などによるカウンセリング
心の病気の治療法は大きく二つ
【精神療法】
患者さんと治療者(医師や臨床心理士)が話をするなかで、徐々に心の問題を軽くし、解決していく治療法です。精神療法には、おもにつぎのようなものがあります。
●支持的精神療法
治療者は、患者さんの話を十分に聞いて、悩みや不安を親身に受け止めます。すべての精神療法の基本です。
●カウンセリング
患者さんが、カウンセラー(医師や臨床心理士)との対話をとおして、自分で問題を解決できるようになることを目ざします(カウンセリングでできること)。
●認知療法
極端にかたよったもののとらえ方や感じ方(認知のゆがみ)を修正して、柔軟な考え方ができるようします。
●精神分析療法
心に浮かんだことのすべてをことばにする自由連想法で、心の奥に隠された抑圧やコンプレックスをあきらかにします。
●家族療法
精神的な問題は、患者さん本人だけでなく家族関係にもかかわるという考え方から、家族を含めて面接し、いっしょに解決していきます。
そのほか、作業療法(おもに入院中の患者さんが、園芸、土木、動物飼育など、生産的な活動をすることで、現実認識を養い、心身を活性化させる治療法。社会復帰へのリハビリ的療法といえます)、行動療法(患者さんの症状や問題となる行為は、これまでの生活体験のなかで獲得したものと考えます。なぜそうなったかをあきらかにし、望ましい考え方や行動を身につけて症状を改善していきます)、交流分析療法(アメリカの精神科医・バーンによって創世された精神療法。精神分析療法の理論をわかりやすく改良したもので、自我や自分の対人関係の「くせ」を知り、改善することを目的とします)、森田療法(日本人の精神科医、森田正馬博士によって考案された精神療法。症状を取り除こうとするのでなく、「あるがまま」を受け入れ、障害を克服しようという方法。通常、入院治療になります)、芸術療法などがあります。
【薬物療法】
心の病気の薬というと「薬が人格に作用したり性格が変わるのでは」とか、「薬をやめられなくなったらどうしよう」といった誤解や不安を持つ人が多いようです。しかし、薬が人格に影響することはありませんし、医師の指示に従って用量や回数を守れば、依存症になることもありません。
たいせつなことは、なぜその薬が必要なのか、どんな効果があるのかなど、医師から説明をよく聞き、納得して服用すること。また、副作用がでてつらいときは、遠慮せず医師に相談しましょう。薬の種類や量を変えたり、副作用を軽減する薬を処方してくれます。
なお、妊娠・授乳中の服用については、医師に相談します。妊娠・授乳中のときや妊娠の可能性がある場合は、はっきりと医師に伝えましょう。
自分らしくいることが心の健康の基本です
自分らしさを伸ばすために、ふだんからつぎのことを心がけましょう。
心の病気についてもっと知る
現代社会と症候群自傷行為をする理由
児童虐待はなぜ起こる?
現代の病・ひきこもり
レイプ被害後の心のケア
自己臭恐怖と醜形恐怖
PTSDとは
睡眠の障害
母子分離不安とは……
ドメスティック・バイオレンス(DV)
性同一性障害とは
子どもの心の病気心の専門科でよく出される薬
うつ病になりやすいのはこんなタイプ
心身症はこんなところにも現れる
ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。
本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。
掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。