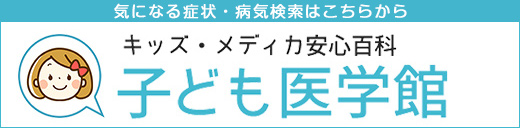注意したい年代
40代、50代、60代。
どんな病気?
卵巣がんは、卵巣にできる悪性のがんです。卵巣に発生する卵巣腫瘍は、大きく分けると良性群、低悪性(中間)群、悪性群の三つとなり、悪性群の代表ががんです。
卵巣がんには、原発性(最初から卵巣がんとして発生する)と転移性(胃がんや乳がんから転移したもの)があります。もっとも多いのは、卵巣の表面をおおっている上皮細胞から発生する原発性の腺がんで、一般に卵巣がんと呼んでいるのは、これをさします。
卵巣がんは近年、日本でも増加の傾向にあります。20年ほど前は、その発生率はアメリカの3分の1でしたが、いまでは約3分の2となりました。患者数は、子宮がんにくらべると少ないのですが、早期発見がむずかしく、婦人科のがんのなかではもっとも治りにくいがんで、最近では卵巣がんによる死亡者数が子宮がんを超えてきました。
かかりやすい人
良性の卵巣腫瘍のうち、その3分の2は、20~40歳代前半にみられます。悪性の卵巣がんがもっとも多いのは40~60歳代。ピークは50歳代です。しかし、実際には10歳代から高齢者にまで幅広くみられ、年齢を問わず発生するのが特徴です。
また、月経不順、未婚、妊娠・出産の経験がない人や少ない人、そのほか更年期以降、高齢になるほど、かかる危険性が高くなると考えられています。
原因
原因の多くは不明ですが、唯一わかっているのは排卵回数との関係です。卵胞が成熟し、卵巣の表面で破れて卵子が飛び出す現象が排卵です。この卵子が飛び出すときに卵巣が傷つき、その傷から上皮が卵巣内に入り込み、その上皮がホルモンの影響を受けて、がん化すると考えられています。
女性の晩婚化や少子化で出産回数が減ったため、現代の女性は、昔の女性にくらべて排卵の回数がふえています。
1回妊娠をすると、授乳期間も含めると1年から1年半は排卵がないので、そのあいだ、卵巣は休養ができます。昔のように子だくさんの時代は、卵巣が十分に休養できたのですが、現代の女性は卵巣を休ませることなく使っていることになり、排卵時に卵巣を傷つける回数が多いのが、卵巣がん増加の要因の一つと考えられています。
また、月経(排卵)が開始する年齢が早くなってきたことや、動物性脂肪の過剰摂取もいわれています。
がんの進行と症状
がんの進行の度合いによって
卵巣がんは「サイレント・キャンサー」(なにも語ってくれないがん)といわれ、初期はほとんど無症状です。
がんが大きくなってはじめて、下腹部にしこりをふれたり、おなかがふくれたり、トイレが近いとか下腹部痛などの自覚症状がでてきます。症状が現れたときには、すでに手遅れということも少なくありません。
おなかのふくらみを、太りすぎとまちがえて、ダイエットをつづけていたというケースもあります。
また、大きくなったがんがねじれて激痛が起こり、救急車で運ばれて、はじめてがんが発見されるというケースもあります。
検診
卵巣がんは、小さいうちに見つけるのはなかなか困難です。
異変を早く知るためには、子宮がんの検診の際に、卵巣をくわしく観察することができる経腟エコー(超音波検査)で、卵巣がんの検査もしてもらうことがたいせつです。
卵巣がんの場合、子宮がんのような集団検診はごくかぎられた地域を除いて行われていません。自費になりますが、ぜひ積極的に受診してください。
検査と診断
卵巣がんの診断には、つぎの順番で検査を行います。
治療
根治手術(子宮全摘、両側の卵巣卵管摘出、大網(胃から垂れ下がった腹膜の一部で、横行結腸と小腸のあいだをおおう膜)切除、リンパ節切除)を行い、さらに抗がん剤による化学療法を追加するのが、原則的な治療法です。がんが進行していて完全手術(がんをすべて取り除く)が不可能な場合は、まず手術前に化学療法を行い、ついで完全手術を目ざします。とくに、抗がん剤のシスプラチンの開発によって、延命率がかなり高くなってきました。
抗がん剤の副作用としては、嘔吐、脱毛、白血球や血小板が減少する骨髄障害、腎機能障害などがみられます。
なお、がんが再発した場合には、放射線を用いることがあります。
[片側の卵巣、卵管のみを取る]
●保存手術
腫瘍がある側の卵巣・卵管だけを切除する手術です。
低悪性群や悪性群でも、
[両側卵巣やその周囲も取る]
●根治手術
両側卵巣、卵管、子宮、大網、骨盤から傍腹部大動脈までのリンパ節を切除する手術です。必要に応じて腸の切除を行うこともあります。しかし、腫瘍が完全に摘出できるのは、
[化学療法後に再度手術をする]
●セカンド・ルック手術
初回の手術で、腫瘍の取り残しがあった場合、術後、抗がん剤で化学療法を行って腫瘍を小さくし、再び手術をして完全切除をめざすものです。2回め、3回めの手術が行われることもあり、この方法で治癒する例もあります。
がんが進行して、手術がむずかしい場合は、先に抗がん剤を投与して、腫瘍を小さくしてから手術を行い、術後、再び抗がん剤の投与をつづけます。
治療後の定期検診
卵巣がんの再発は少なくありません。手術で腫瘍を完全に取った場合でも、再発することがあります。再発がもっともよく現れるのは治療後3年以内ですが、5年間は主治医による定期検査が必要です。
あなたへのひとこと
退院後約1か月で回復し、セックスは術後2か月ほどで再開できます。ただ両側の卵巣を摘出すると、更年期症状(更年期に起こりやすいからだの不調・トラブル)が現れたり、腟粘膜にうるおいを与えていた卵胞ホルモンが作用しなくなるため、性交痛が起こることもあります。女性ホルモン剤の服用や、潤滑ゼリーなどの塗り薬の使用で解決できるので、医師に相談しましょう。
抗がん剤の副作用で脱毛しているときは、パーマや染髪は避けます。
ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。
本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。
掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。