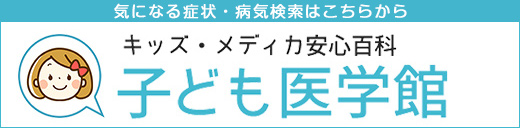病気にかかりながら抵抗力をつけていく
生まれた直後の赤ちゃんは、お母さんから、いろいろな感染症に対する抵抗力をもらい受けていますが、それも半年弱で消えてしまいます。その後は、子どもははじめて出会う病原体の危険にさらされることになります。
子どもは免疫がほとんどないうえ、からだの防御機能が十分にできあがっていないので、感染症にかかりやすいのです。受診の機会もふえます。信頼できる小児科のホームドクター(ホームドクターの選び方)を決めておきましょう。
逆のいい方をすれば、子どもはいろいろな病気にかかりながら免疫を獲得し、抵抗力を増していくということがいえます。子どもの感染症で心配なのは、人ごみでうつされる病気の場合です。いくつかの病気は予防接種である程度防ぐことができます。予防接種があるものは、時期がきたら早めに接種をすませることが、子どもを守るたいせつなポイントです。
予防接種は、子どもを重大な病気から守る最良の選択
欧米では、乳幼児を病気から守るのは大人の責任という考えが定着しており、早めに予防接種をすませます。
副反応は皆無と聞かないと、日本の親は不安なのかもしれませんが、自然感染して後遺症が残ったり、死亡したりする危険率のほうが、予防接種の副反応の危険率よりずっと高いのです。予防接種は、自分のからだを守るだけでなく、人にうつす危険も減らします
予防接種には、BCG、三種混合、ポリオ(急性灰白髄炎)(ポリオウイルスが感染し、手足、とくに足にマヒが現れる病気。重症化せず、かぜ程度で終わる場合もありますが、マヒが残ることもあります。日本での自然発生は、最近みられなくなりました)、はしか(麻疹)、風疹混合ワクチンなどの国が勧めている勧奨接種と、水ぼうそう(水痘)、おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)、インフルエンザ、B型肝炎などの任意接種があります。日本脳炎(日本脳炎ウイルスを持つブタの血を吸ったコガタアカイエカがウイルスを人に運び、脳をおかす病気)は、平成17年5月に厚生労働省の通達により勧奨接種を差し控えています。また、接種方法には、保健所などで集団で行う集団接種と、かかりつけ医で受ける個別接種がありますが、全体的には個別接種が主流になりつつあります。
予防接種の実施は市区町村などの地方自治体の方針で行われますので、まず住んでいる地域の自治体の方針を知っておきましょう。
ワクチンのタイプと受ける間隔
●生ワクチン
予防接種の種類 BCG・ポリオ・麻疹・風疹・おたふくかぜ・水ぼうそう
間隔 接種後ほかの病気の予防接種を受ける場合は、4週間あけてから接種する。
●不活化ワクチン・トキソイド
予防接種の種類 三種混合・日本脳炎・インフルエンザ・B型肝炎
間隔接種後ほかの病気の予防接種を受ける場合は1週間あけてから接種する。
はしか(麻疹)
症状
高熱が急にでて、せき、鼻水、目やにがひどくなり、食欲不振や頭痛も起こします。発熱は2~3日つづき、その後、一時的に半日ぐらい熱が下がり、また上がります。このときに発疹が出はじめ、胸やおなかから手足に広がり、口の中にコプリック斑という小さな白い斑点ができます。場合によっては肺炎や脳炎を合併、死亡するケースもあります。潜伏期間は10~12日。
治療
特効薬はありません。解熱剤か鎮咳剤で体力の消耗を防ぎます。
ケア
脱水症状を防ぐために、果汁、イオン飲料など水分を十分に与えます。
水ぼうそう(水痘)
症状
虫に刺されたような小さなかゆみのある赤い発疹が出て、全身に広がります。発疹は水ぶくれになり、3~4日でかさぶたになります。すべてがかさぶたになるまで、10日~2週間ほどかかります。潜伏期間は2~3週間。子どもはまれですが、同じウイルスで帯状疱疹になることも。
治療
抗ウイルス剤があります。かならずしも抗ウイルス剤を服用する必要はありませんが、乳児や中学生以上の子どもが感染したり、皮膚に病気がある場合は重症化しやすいので、発症後2日以内なら服用が効果的です。
ケア
水疱をかきむしって細菌に感染しないように清潔を心がけて。
風疹
症状
細かい赤い発疹が全身に広がりますが、だいたい3日で消えることから別名「三日ばしか」ともいわれます。のどが赤く腫れたり、首のうしろや頸部のリンパ腺が腫れて痛みます。潜伏期間は2~3週間。
治療
特効薬はありません。発熱があれば水分を十分にとり、安静にします。
ケア
脱水症状を防ぐために果汁やイオン飲料などで十分に水分補給を。
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)
症状
熱とともに耳下腺が腫れ、痛みます。腫れは片方だけのときもあります。髄膜炎などの合併症を起こすこともありますが、重症化しないものがほとんどです。潜伏期間は16~18日。
治療
特効薬はありません。水分を補給し、熱や痛みには解熱剤を使います。
ケア
口をあけるのがつらいのでスープや果汁など、かまなくていいものを。
冬期嘔吐下痢症
症状
白色便が特徴です。はじめは嘔吐もみられ、その後下痢だけになります。下痢は多い場合、1日に10数回もあり、米のとぎ汁のような色のものから、クリーム色のこともあります。同時に腹痛や発熱も多くみられます。
治療
症状が強ければ早めに受診します。水分を少量ずつ与え脱水予防を。
ケア
吐き気がなくなったら、食事は薄めたミルクや水分の多い重湯から。
りんご病(伝染性紅斑)
症状
両ほおがりんごのように赤くなるので、この俗称があります。熱はでても37度ぐらいで、まずほおが赤くなり、1日ぐらい遅れて手足や胴にも発疹が広がり、発疹と発疹がくっついてレース様や網目状になります。関節痛などを訴えることもありますが、多くは発疹以外に症状がなく、心配のない病気です。潜伏期間は7~16日。
治療
特別な治療法はありません。発疹の手当てなどの対症療法を行います。
ケア
ふつうに生活してよいでしょう。
ヘルパンギーナ
症状
夏かぜの一種で、いきなり高熱がでて、のどの奥のあたりに赤い小さな水疱がたくさんできます。この水疱は2、3日で破れて潰瘍化して、のどが痛みます。潜伏期間は2~4日。
治療
特別な治療法はありません。自然に治るのを待ちます。水分がとれないときは、入院して点滴が必要です。
ケア
水分を十分にとり、豆腐やゼリーなどの刺激のないものを与えます。
手足口病
症状
夏かぜの一種ともいえるもので、手、足、口に水疱ができます。口の中にできた水疱が破れて痛む以外は、心配な病気ではありません。熱はでても軽い発熱です。潜伏期間は3~6日。
治療
特効薬はなく、口の中が痛むときは口内炎用の軟膏を塗ります。
ケア
豆腐やゼリーなど、薄味でのどごしのいいものを与えます。
咽頭結膜熱(プール熱)
症状
だるそうでかぜっぽいと思っていると、涙目になり充血して結膜炎を起こし、40度近い高熱がでます。関節痛や頭痛、腹痛や下痢をともなうことも。熱は3~4日つづき、1週間で快方に向かいます。潜伏期間は5~6日。
治療
熱には解熱剤、結膜炎には点眼薬などの対症療法を行います。
ケア
感染力が強いので、家族間でのタオルなどの共用を避けます。水分を十分にとり、安静にしてすごします。
インフルエンザ
症状
もっとも多い症状は発熱と悪寒で、ほかに、せき、頭痛、のどの痛み、疲労感、鼻水、関節痛、下痢などもみられます。ごくまれに脳炎や脳症(インフルエンザにかかった子どもが、高熱、けいれん、意識障害を起こして発症。解熱剤のジクロフェナクナトリウムなどの関与が指摘されています)を合併することがあります。全身症状がよくないときは早めに再受診することがたいせつです。潜伏期間は1~3日。
治療
高熱に対しては医師の指示どおりに解熱剤を使用します。発症後48時間以内に服用すれば有効な抗ウイルス剤があります。
ケア
水分を十分にとり、安静に。
溶連菌感染症(猩紅熱)
症状
のどが腫れて痛み、多くは発熱をともない、赤く細かい発疹が首や胸から全身に広がります。舌も赤く腫れて、ぶつぶつしたイチゴ状になります。ときに合併症として、腎炎や心臓弁膜症の原因ともなるリウマチ熱を起こすことがあるので、かならず受診して完治させます。潜伏期間は2~7日。
治療
合併症を防ぐために、最低10日間は抗生物質を飲みます。細菌が原因なので、何度もかかることがあります。
ケア
抗生物質を服用後、3~4日でふつうの生活にもどれます。状態がよければ生活の制限はあまりありません。
百日ぜき
症状
発熱もなく、せきがしだいにふえ、夜にせき込むようになります。やがて、コンコンコーンと短いせきがつづき、その後ヒューと息を吸い込む特有のせきがでます。潜伏期間は7~10日。
治療
発症の初期なら抗生物質の投与が有効。その他は対症療法を行います。
注意
予防接種をしていても軽くかかることもあります。医師に予防接種の有無を伝えます
突発性発疹
症状
2歳以下の子どもに多くみられます。急な高熱が3日ほどつづき、熱が下がると、胸やおなかを中心に発疹が広がります。
治療
特効薬はありませんが、心配な病気ではありません。
髄膜炎
症状
首がかたくつっぱり、曲げられなくなり、頭痛、けいれん、嘔吐などがみられます。
細菌性のものは、脳に障害を残すこともありますが、ウイルス性のものは、適切な治療を受けることにより、ほとんどが治ります。
しかしなかには、単純ヘルペスなど、重篤になるものもあります。
治療
細菌性のものには抗生物質を使用します。ウイルス性のものはヘルペスを除いて特効薬はないので、輸液など症状に応じた治療をします。
マイコプラズマ肺炎
症状
かぜの症状につづいて、38度以上の高熱、せき、倦怠感、頭痛、食欲不振などがみられます。ほうっておくと熱とせきがしつこくつづきます。
治療
抗生物質が有効です。10日前後で症状がおさまります。
子どもの感染症についてもっと知る
おもな感染症ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。
本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。
掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。