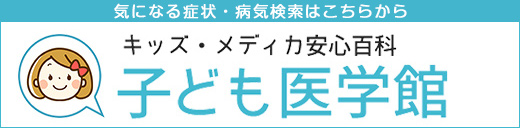市販薬の使い方と購入時の注意
市販薬は病院にいくというわずらわしさがなく、薬局や薬店などで手軽に購入できる利点があります。ただし、万人向けの薬なので、薬効成分は処方薬より少なくなっています。症状が軽く、病院にいくほどでもないというときに利用するのに向いています。
市販薬を購入するときは、できれば薬剤師にそのときの症状をくわしく話し、いちばんよい薬を選んでもらうようにしましょう。かぜ薬はこれ、胃腸薬はこれと決めている人もいますが、症状に合わせて飲み分けるのが、市販薬のじょうずな使い方です。
ちなみに、薬局には薬剤師がいることが法的に義務づけられていますが、薬店やドラッグストアに薬剤師が常駐しているとはかぎりません。
市販薬にも副作用がある
市販薬は処方薬にくらべて薬効成分が少ないとはいえ、薬ですから副作用があります。最近では、より強い効果をだすために、薬効成分量を多くしている市販薬もあります。
市販薬どうしの併用で副作用がでる場合もあるので、添付の説明書をよく読んで気をつけましょう。
処方薬をすでに使用している場合は、医師または薬剤師に相談してから、市販薬を使うようにします。
市販薬の種類
解熱鎮痛剤
熱を下げて発熱による不快な症状をやわらげたり、頭痛や生理痛、歯痛などの痛みをやわらげる薬です。解熱鎮痛剤は病気そのものを治す薬ではなく、症状をやわらげる対症療法薬です。
添付の説明書にも書かれているように、一定量を飲んでも効果が現れない場合は薬を追加するのではなく、服用を中止して受診しましょう。
総合感冒薬
いわゆるかぜ薬で、かぜの諸症状をやわらげるために用います。
かぜの原因の多くはウイルスによるものですが、ウイルスをやっつける特効薬はありません。かぜ薬は不快な症状によるからだの負担を軽くするために飲むものです。睡眠と栄養を十分にとって、自己免疫力でウイルスを撃退しましょう。
かぜの症状は多様なので、かぜ薬もいろいろな種類が出ています。熱があるときは解熱鎮痛剤、鼻の症状には鼻炎の薬(抗ヒスタミン剤)、のどの痛みなどには消炎酵素剤、せきには鎮咳剤、たんには去痰剤といったように、症状に合わせて飲み分けましょう。
かぜ薬には漢方成分が使われているものも多くあります。漢方胃腸薬などと併用すると、漢方成分による副作用がでる場合もあるので、かならず薬剤師に相談しましょう。
また、かぜのような症状があっても、かならずしもかぜとはかぎりません。薬を飲んでも効果がないときは、受診します。
抗アレルギー剤
アレルギー性鼻炎や花粉症、アレルギー性皮膚炎など、アレルギーによる症状をやわらげるための薬です。
もっとも多く使われるのは抗ヒスタミン剤で、薬効成分の含有量も比較的多いため、眠気やのどの渇きといった副作用がでやすいのが特徴です。抗アレルギー剤は長く飲みつづける場合が多いので、飲んでいるうちに副作用に慣れてしまうこともありますが、つらい場合は薬を替えるといいでしょう。
服用回数は1日2~3回から1回へと減る傾向にあり、1回の服用で長時間効くものが多くなりました。説明書をよく読んで、飲みすぎないように気をつけます。
胃腸薬
消化不良、食欲不振、胃酸過多、胃痛、腹痛、下痢など、胃腸の症状にはいろいろなものがあります。総合胃腸薬はそれらの諸症状に対応しているもので、ちょっとした胃の不快症状に用いるのに適しています。
胸やけするなど、症状がはっきりしている場合は、症状別につくられた胃腸薬のほうが効果があります。
便秘薬
便秘薬には腸を刺激して排便をうながすものや、便を膨張させ、それが刺激となり、排便をうながすものなどがあり、生薬も漢方薬として多く使われています。生薬でも副作用はあるので、ほかの薬との併用に気をつけます。
便秘薬は使いはじめるとくせになり、しだいに量がふえていく傾向があります。なるべく薬の力に頼らずに排便するよう心がけましょう(便秘)。
また、ビフィズス菌や乳酸菌などを配合した整腸剤も、腸内環境を整えることで便通をよくする効果があり、便秘薬としても使われています。
点眼薬(目薬)
目の疲れ、かゆみ、充血、ドライアイ、目の炎症など、さまざまな目の症状を緩和する薬で、自分の症状に合ったものを選ぶようにします。
目薬はさしたときの爽快感から常用しがちですが、症状がおさまったら使用をやめましょう。
また家族との共用はしないこと。開封後1か月以内に使いきります。
貼り薬・塗り薬
肩こりや腰痛、筋肉痛などに効く湿布薬・塗り薬、皮膚の乾燥や炎症を抑える塗り薬などがあります。
貼り薬や塗り薬は効果をだすために多く使いがちですが、薬効成分量が多いものもあるので、用法・用量を守るようにします。
飲み薬でなくても副作用はあります。添付の説明書をよく読んで、薬の併用にも気をつけましょう。
ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。
本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。
掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。