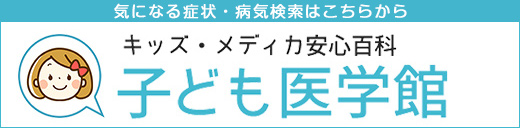注意したい年代
20代、30代、40代。
バルトリン腺は、小陰唇のつけ根付近の、腟の入り口の左右にある小さな分泌腺で、性的興奮があったときに、分泌物を出す器官です。
この分泌腺の開口部に大腸菌などの細菌が侵入し、炎症を起こしてしまうのがバルトリン腺炎で、外陰部で多くみられる病気の一つです。バルトリン腺炎が化膿するとバルトリン腺膿瘍に、またバルトリン腺炎をくり返すと、バルトリン腺嚢腫を起こします。
以前は、原因の多くは淋菌によるものでしたが、最近は減ってきています。治療しても、再発することが多い病気です。再発を頻繁にくり返すときには、バルトリン腺全体を摘出する場合もあります。医師と相談しながら治療しましょう。
バルトリン腺炎・バルトリン腺膿瘍
どんな病気?
バルトリン腺炎は、バルトリン腺が大腸菌などの細菌に感染して、炎症を起こした状態です。
その炎症が化膿して、腫れた部分に膿がたまってしまった状態をバルトリン腺膿瘍といいます。
原因
汚い手で外陰部をさわったり、セックスの際に、バルトリン腺の開口部からブドウ球菌や連鎖球菌、大腸菌、淋菌などが侵入して起こります。外陰炎などの炎症に引きつづいて起こることもあります。
症状
ふつうは、左右のどちらかのバルトリン腺が赤く腫れてしこり、痛みます。バルトリン腺膿瘍になると、痛みは強くなり、腫れた部分が熱をもった感じがします。腫れは、鶏卵大にもなることがあります。
炎症がはげしいと、痛みと腫れのために歩くことができなくなったり、排尿が困難になるほどです。熱がでることもあります。
診断
腫れを触診すると、バルトリン腺に一致しているのがわかります。通常は、しこりにたまっている分泌液を注射針で吸い取り、細胞培養検査をして、原因菌を特定します。
バルトリン腺の中にたまった内容液を注出することが、治療を兼ねることもありますが、内容液を抜くだけでは、多くの場合再発します。
治療
原因菌を特定し、その菌に合った抗生物質を内服します。症状によっては、消炎剤や鎮痛剤を使います。
腫れが大きいときや膿がたまっているときは、穿刺や切開をして、中にたまった膿を出します。
再発をくり返す場合は、患部を切開して膿を出し、バルトリン腺の出口がふさがらないように口をつくる造袋術という手術を行います。あるいは、摘出術といって、バルトリン腺そのものを取ってしまう手術で、根治します。
局部麻酔をかけて行う造袋術は、外来でもかんたんに行える手術です。
あなたへのひとこと
炎症がはげしいと、すぐに切開などの治療ができないこともあります。異常に気がついたら早めに受診しましょう。また日ごろから、外陰部の清潔を心がけ、セックスの前後にはシャワーを浴びるなど不潔にならないように気をつけます。
再発をくり返すときは、バルトリン腺を摘出するなど、根本的な治療を検討したほうがよい場合もあります。
バルトリン腺の摘出手術は、通常、1~2日入院し、その後も1週間ほどの通院が必要ですが、手術そのものはそれほどむずかしいものではありません。何度も炎症に悩まされるよりは、思いきって手術で完治させることを選択してもよいでしょう。
ほとんどの場合、バルトリン腺炎を起こすのは片方だけなので、性交時の分泌液が不足するようなことはありません。不安なら医師とよく相談しましょう。
バルトリン腺嚢腫
どんな病気?
炎症をくり返すうちにバルトリン腺の開口部がふさがって、外に分泌されるはずの粘液がその内部にたまって、袋のような嚢腫ができることがあります。この状態が、バルトリン腺嚢腫です。分泌物がたまっているだけで、炎症をともなわないので、痛みはなく、バルトリン腺のある腟の入り口付近の腫れ以外に自覚症状はありません。そのため、ある程度腫れが大きくなるまで、気がつかないこともめずらしくありません。
原因
バルトリン腺の開口部がふさがる原因はよくわかっていませんが、バルトリン腺の炎症をくり返すと、嚢腫ができやすくなるといわれています。
症状
腟の入り口付近のバルトリン腺が腫れてしこります。しこりは通常、左右のどちらか一方だけに発生します。しこりはだんだん大きくなり、ときには鶏卵ほどの大きさになることもあります。痛みはほとんどありません。腫れやしこりが大きくなると、外陰部に違和感を感じ、歩きにくくなります。
診断
腫れている部分を触診すると、バルトリン腺の位置と一致するので、診断は容易です。
治療
嚢腫が小さいうちは、しばらくようすをみますが、約3~4cm以上になったら、切開して分泌物を外に排出したり、嚢腫を摘出します。
あなたへのひとこと
外陰部の腫れに気がついたら大きくなる前に受診し、治療法について相談しましょう。
ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。
本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。
掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。