「助産婦」から「助産師」へ名称変更
今まで何度かベビカム会員のみなさんに、男性助産師のことや助産婦の名称変更などのアンケートに答えていただきましたが、昨年の12月6日に『保健婦助産婦看護婦法』の改正があり、名称変更がありました。
「婦」から「師」への変更で、「助産婦」も「助産師」となりました。
そこで、私が連載している『助産婦日記』も『助産師日記』に変えなければいけないのですが、私はこのまま『助産婦日記』でいきたいなと思っています。
そもそも「師」に変更した理由は、助産婦の社会的地位の向上や男女共同参画社会だからということのようですが、「助産婦」という言葉には、産婦(妊婦・褥婦)を助ける・女性に寄り添うなど、女性にとって親しみやすさがあったように思います。
かつては産婆と言われ、それが助産婦に変わり、今度は助産師に…。名前だけをみれば10年もすれば、「助産師」という呼び名も馴染んでくるのでしょうか。
病院内での名札も変更
病院では、名札が「助産婦」から「助産師」に変わり、「婦長」も「師長」に変わりました。「師長」と呼ばれても、誰のことを指しているのか違和感が残ります(「師長」といえば、「市長」を想像しますよね)。しかし、今でもお母様方から助産婦さんと呼ばれ、ホッとしています。
これからも、助産婦として女性に寄り添うようなかかわりをしていきたい、と思っています。私は、人との出会いに偶然よりも縁を感じます。たまたま、その勤務になりお産した女性と出会ったとしても、不思議な引き合わせを感じます。
人から人への結びつきが、私の力になっているのだと思います。そのような思いで、これからも出会いを楽しみにしながら『助産婦日記』を書いていきたいと思っています。
名称変更と今後の動き
今回の名称変更の法律には、「助産師は女子とする。」となり、附帯事項(下記参照)も決議されました。ただ、男性助産師のことや助産師教育のことなど、これからの動きも気になるところです。
しかし、一番大切なのは、産む環境を整えることや育児のための支援など私たち助産婦のやることが、まだまだあるということです。まだまだ、出産環境は施設ごとで偏っていたり、育児をしている方に援助の手が行き渡っていません。
病院という組織にいると、自分自身やりたいことができなかったり、不本意なこともたくさんあります。イヤになることもたびたびですが、いろいろな方からパワーをいただき「また、がんばろう」と思えてきます。
みなさんは、助産師に変わったことをどう思いますか? 助産師に対して何を期待されますか? ぜひ教えてください。
【参考1】『保健婦助産婦看護婦法』附帯事項
- 1.出産に関するケアを受ける者の意向が尊重され、それぞれの者にあったサービスの提供が行われるよう、必要な環境の整備に努めること。
- 2.助産師教育については、十分な出産介助実習が経簸できるようにする等、その充実に努めること。
- 3.保健師、助産師、看護師等の看護職員については、その責任と社会的使命の重大さにかんがみ、それぞれの職種が果たしている機能の充実強化に向けて、教育環境の改善、人員増等の施策を講ずること。
【参考2】「助産婦名称変更に関するアンケート」結果
(インターネット(ベビカム)にて、お産サポートJapan準備会が2991年11月19日より11月26日かけて実施。有効回答数172人)
「助産師」という名称への変更反対は66人、38パーセントもありました。また、「男性助産婦(師)の導入」は、反対という意見が103人、60パーセントと過半数を超えています。主な理由としては、「男の人には出産を経験できないし、気持ちをわかってもらえない」、「男性だとリラックスできない」、「デリケートな部分が多いので男性ではいやだ」という意見が上がりました。賛成という人でも、「選べる権利がほしい」、「仕事を分けるなら」という条件を付けた方がほとんどでした。
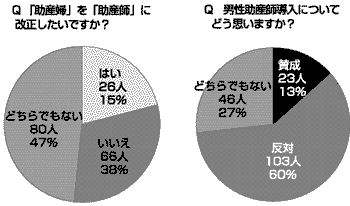
(2002.5)









