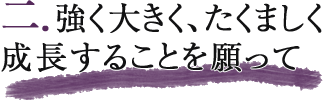画像提供:真多呂人形
端午の節句は奈良時代に中国から入ってきました。平安時代には貴族が病気や災厄から身を守る行事だったとも言われています。もともと端午というのは月の端(はじめ)の午(うま)の日という意味がり、これに午(ご)=5の語呂あわせが重なり、毎年5月5日を端午の節句と呼ぶようになったそうです。また端午の節句は時代とともに少しずつ変化し今も節句行事のひとつとして残っています。

端午の節句は鎌倉時代あたりから「菖蒲」と「尚武」が同じ読み方ということと、菖蒲の葉が鋭い剣に似ていることか、厄除けとして男の子の行事となったといわれています。五月人形や鎧兜は、身を守り、武士のように強くたくましく成長してほしいという願いを込めて飾られるようになったそうです。また、鯉のぼりは中国の黄河という大きな川の流れの速い竜門を登りきった鯉が竜に化けるという話から、子どもの立身出世、成功して立派に名をあげるという願いを込めて、鯉のぼりを飾るようになりました。

画像提供:高島屋
五月人形や鎧兜を飾る時期はとくに決められていることはありませんが、いつ飾れば良いのか気になるところですよね。鯉のぼりのような「外飾り」に対して、家の中に飾る五月人形や鎧兜は「内飾り」と呼ばれています。内飾りも外飾りも飾る時期は同じで一般的には春のお彼岸を過ぎた4月上旬ごろから、内飾り、外飾りと順に飾ることが一般的とされています。